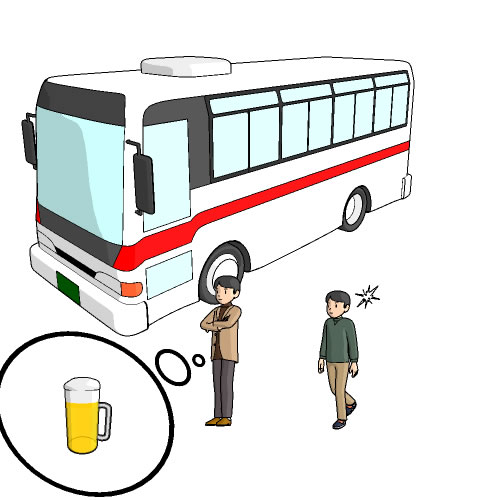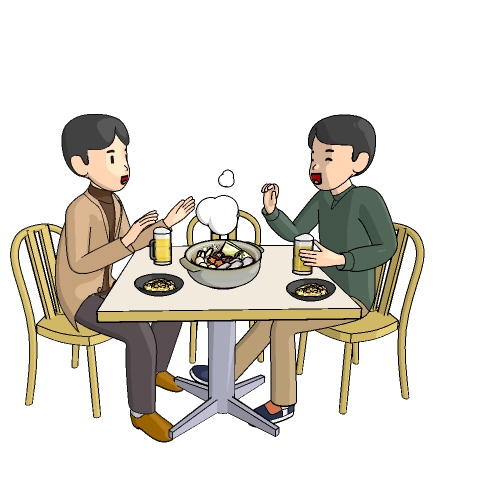健康ランドに出かけ、思ったより盛り上がらずにその日の夜に帰ってきた。
このまま帰ってはだめだ。何故だめなのかはわからないが、なんか盛り上がるイベントを自らで発生させてみたいと思った。
私は自宅から
全力ブログ
唐突に思いついて函館に行った話 その3
宿に戻ってぐっすり寝た私は、朝起きて、函館朝市に向かう。

▲また海鮮丼
今度は、別の店で海鮮丼を食べた。いろいろのっかっているので、いろんな味が楽しめていいんじゃないの?という予測に基づくものである。サーモンが凍っていたこと以外はおおむね満足であった。凍ったサーモンは、ご飯の中にうずめて解凍しながら食った。
ごちそうさま。
宿に戻り、もう一泊してこのままうだうだ駅前周辺をうろついて帰ろうかなあと思ったら、「残念ながら満員でして」と、まったく残念そうでない顔で言われてしまった。ちくしょう。
しょうがないので、少し北のほうに電車で移動して、大沼というところに行くことにした。

▲函館駅前のなぞのオブジェ
特急北斗で大沼方面へ。車内はガラガラで、15分くらいでついた。

▲特急北斗車内
大きな地図で見る
大沼は、その名の通り大きな沼が近くにあるのだ。こんだけ大きければ湖と言っても差支えないと思うのだが、何でもでっかい北海道の中では、その程度じゃあまだまだ沼だね、ということなんだろう。

▲車内から見た沼
大沼公園に到着した。地名が写っている写真を撮っておきたくて、これを撮った。

▲間違いなく大沼公園だ
結構都会だった函館と比べて、大沼公園周辺はのどかな感じ。そりゃあ公園だから。

▲大沼公園駅
駅前にはレンタサイクル屋があったが、まあせっかくだし歩いていこうと思って歩き始める。

▲ぐもう
レンタサイクル屋にはなぜか、何体もの熊の剥製があった。観光客がさわりまくるからか、網がかぶせられていた。なるほど、たしかに網がかぶせられてないと私もとりあえず触ってしまうかも知れないなあ。

ときどき車は通るけど、とってものどかな大沼公園。とりあえず、第一の目的は近くの牧場まで行って濃い牛乳を飲むことだ。

▲大沼遊園地?
道中、さびだらけの大沼遊園地の門を発見。門の向こうにはどう見ても何もないので、閉鎖されてしまったんだろうか。それとも奥の方で見つからないようにこっそりやっているのか。どっちにしても、特に遊園地に行きたいとは思わなかったので、ふうんと思いながら通過した。
しかし、なかなか目的地に着かないな。そう思って地図を見ると、縮尺が1cmあたり650mだった。1cmあたり200mくらいかなあという感覚で歩いていたので、距離はおよそ3倍である。結局30分ほど歩いて、山川牧場に到着した。

▲牛乳ゲット!
店のとこには常時人がいないので、通りすがりの牧場の人を捕まえて、牛乳くれよとお願いするシステムになっている。その場で飲むなら90円、ということであった。ビン代の関係で、持って帰る場合とその場で飲む場合とで料金が違うらしい。
そして、初めて飲んだ北海道の牛乳は、確かに濃かった。
ああ、こんな感じに濃いのか。どろどろさはなく、なんというか牛乳に生クリームを入れて飲んでいるようなそんな感じだ。牛乳を飲むとおなかがごろごろする私だったが、とくにごろごろは起きなかった。ごちそうさま、おいしかった。

▲牛の時計
すぐ隣で、ローストビーフサンドを売っていたので、買うことにする。
作るのに3,4分かかるとのことで、しばし待つことに。目の前には、手作りの牛時計がならんでいた。ああ、いい天気だなあ。
数分でローストビーフサンドが出来上がり。店の人と、どこから来られたんですか、東京です、へえーこっちは寒いでしょう、ええほんと寒いですねー、僕らも上着着こんでるくらいで、へええー、という会話を交わしたりした。
一人旅をすると、なんだか人との会話に飢えるので、その程度の軽めの会話はとても楽しい。

▲うもう
乳をしぼる小屋をのぞいてみると、牛がちらりとこっちを見た。草をもぐもぐもぐもぐ食っている。
放牧はされていないのかなあ。
ローストビーフサンドは弁当代わりにおいておくことにして、ふと気付いたのだが、このあとステーキを食いに行こうと思っていたのだ。
うーん…、まあいいか。
とりあえず、この周辺をぶらつくには徒歩だときついなと学習した私は、駅まで戻ってレンタサイクルを借りた。閉店まで借りて1,000円だ。
店の人に簡単な説明を受ける。鍵はついてますけど、使わなくていいです、盗まれませんから、と言われた。思わず、へえーいい所ですねーと言ってしまう。それは自転車がボロだから盗むやつぁいねーよという意味だったのか、この周辺にはそんな悪い人はいないから、という意味なのか、いやいやきっと、悪い人はいないからという意味に違いないと思い、とりあえず借りた。
新しいきれいな自転車を奨めてもらったのだが、私としては変速つきがよかったので、さびて汚いけど変速のついた自転車をゲット。
びゅんびゅんと大自然の中を走り始めたのだった。<つづく>